伊藤 眞(東京都立大学客員教授)
あまりよく知られていないことかも知れないが、ブギス・マカッサルでは古くから独自の文字が発達し、「ロンタラ」(lontara’)と総称される文字資料(写本)が比較的豊富に存在する。けれども、それらについての研究はこれまで、あまり進捗しているとは言えない。文字資料へのアクセスは限られているし、文字資料に近づくことができたとしても手書きの字体の判読や、切れ目なく続く文章を読み解くには、現地語についての深い知識が求められる。実際、そうした作業を遂行しうる研究者は現地においても、ましてや海外においても、そう多くは見出せないからである。こうした状況にあるロンタラ研究に今後、海外の研究者がたずさわろうとするならば、現地語に習熟すること、そして現地の研究者との間に協力体制を築くことが必要となるだろう。
今回ここで取り上げるマックナイト、ムフリス・パエニ、ムフリス・ハドラウィ三者による共編訳『ブギス・ボネ年代記』は、そうした協力関係に基づくひとつの成果である。著者の一人であるマックナイトは1970年代には南スラウェシにおいて歴史・考古学的調査を開始し、現地のハサヌディン大学と長きにわたる友好関係を築き、共著者であるムフリス・パエニ、ムフリス・ハドラウィらと交流を深めた。彼は、ロンタラ研究に早い時期から関心を抱き、ブギスの強国であったボネのロンタラのひとつ、すなわち「ボネ年代記」(当該の写本にはタイトルは付けられていないが、便宜上筆者はこう呼ぶことにする)の翻訳に力を注いだ。その成果が、「ボネ年代記」について考察と詳細な注釈をつけた本書となった。本書の刊行は、その内容のみならず、翻訳作業における協力のあり方を提示した点においても、おそらく、ロンタラ研究史に新たな1頁をつけ加えるものになるに違いない。以下においては、その意義を理解するために、やや遠回りをしながら、これまでのロンタラ研究(ブギス・マカッサル文献学研究)から本書に至るまでの歩みを簡単に振り返ってみることにしたい。
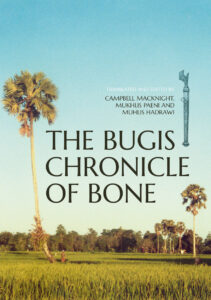
本書は後述のように、ANU出版局のサイトよりpdf版でダウンロード可能である。
1. ロンタラ及びロンタラ文字について
南スラウェシでロンタラと言えば、ブギス・マカッサル語に固有のロンタラ文字(aksara lontara’)で書かれた写本をさす。より正確に言えば、「ロンタラ」は「スレ」(sure’)と区別される。「スレ」に含まれるのは、「イ・ラガリゴ」(I La Galigo)叙事詩に代表されるような文学的ジャンルに属する文字資料であり、一方、「ロンタラ」には、文学的ジャンル以外の文字資料、例えば、系譜、歴史、条約、博物学的記述などが含まれる。
「ロンタラ」ないし「スレ」に書かれる文字は、「ロンタラ文字」(aksara lontara’もしくはhuruf lontara’)と呼ばれるインド系の表音文字である。字形はブギス語、マカッサル語ともに同じで字母の上下左右に母音記号を付けて表記される。字母の数はブギス文字が23、マカッサル文字が19と異なるのは、ブギス語の方が鼻音の字母が多いためである。母音の数もブギス語が6に対してマカッサル語は5と少ない。こうしたロンタラ文字の使用は15世紀はじめ頃に遡る、とコードウェルは1988年の学位論文の中で推定している(Ian Caldwell, South Sulawesi A.D.1300-1600: Ten Bugis Texts, 1988)。ちなみに、ロンタラ文字は、今日の日常生活の中でコミュニケーションの手段としてもはや使用されることはないが、現地の小中学校の「地域語」の授業では教えられている。また街路の名称や村役場の看板などにも、ラテン文字とともにロンタラ文字が使用されている(写真2参照)。最近では、Tシャツの図案などにも利用されている。その意味では、ロンタラ文字は全く過去の文字ではない。

2. マッテス(B.F. Matthes 1818-1908)とブギス・マカッサル文献学
ブギス・マカッサル文献学の基礎を築いた人物として、誰しもが一致してマッテスの名をあげる。実際、マッテス以前にも、ブギス・マカッサルの文字資料について言及した人物はいたが(『ジャワ史』の中で言及したラッフルズもそのひとりである)、ロンタラを系統的に収集し、文献学の対象にしたのは彼が最初だった。
マッテスは19世紀半ば、オランダ聖書協会(Netherlands Bijbelgenootschap=NBG)からマカッサルに派遣された言語学者・聖書翻訳家であり、30年間マカッサルに滞在した。その間、彼はタネテ国(現在のバルー県)の貴族女性チョリ・プジエ(ブギスでは、貴族層の女性が文学伝承の語り部(pasure’)となることが多い)の助けにより計12巻からなる「イ・ラガリゴ」叙事詩の写本NBG188(オランダ聖書協会による文書整理記号)を収集した。この写本は、数ある異本の中で、内容的に最も一貫性があり、かつ長編であることから、後に翻訳事業の対象として選ばれている。マッテスはその他にも数多くの写本を収集し、それらの一部は『ブギス詞華集全3巻』(Boeginesche Chrestomathie I, II, III, 1864, 1872)、『マカッサル詞華集』(Makassarese Chrestomathie, 1860, 1883)の中に収録されている。さらに、マッテスは、『ブギス語-オランダ語辞書』(Boegineesch-Hollandsch Woordenboek, 1874)、『マカッサル語-オランダ語辞書』(Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek, 1885)を編纂、これらの辞書は今日においても文献学研究に必須な価値を有している。
3. オランダにおけるブギス・マカッサル文献学研究の進展
マッテス以降の文献学研究は、(1)「スレ」を主対象とする文学的文献学研究と、(2)「ロンタラ」を主に扱う歴史学的文献学研究に大別される。(1)を代表する研究者としては、ケルン(R.A. Kern 1875-1958)、センセ(A. A. Cense 1901–1977)が、(2)にはノードュイン(J. Noorduyn 1926-1994)がいる。
ケルンは「イ・ラガリゴ」を誰よりも読み込んだ人物である、とL.アンダヤによって評されている。その理由は、彼の主著である『イ・ラガリゴ写本目録I巻・II巻』が、単なる写本目録の域を超えて、ヨーロッパとマカッサル(マッテス研究所)に保管された写本に詳細な要旨と登場人物リストを付け、I・II巻を合わせて1374頁に及ぶ大作だからである(Kern, Rudolf 1939: Catalogus van de Boegineesch, tot den I La Galigo-cyclus behoorende der Leidsch Universiteitsbibliotheek, alsmede van die in andere europeesche bibliotheken, 1939; Catalogus van de Boegineesch, tot den I La Galigo-cyclus behoorende handschriften van Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara te Makassar, 1954)。付言すれば、この大作は、1989年にインドネシア語に翻訳されることで蘇る。ふたつの目録に所収された写本の要旨集はひとつの物語として再編集され、『イ・ラガリゴ』(I La Galigo, 1989、La Side とSagimun M.D.共訳)と題されてガジャマダ大学出版局から刊行される(全1060頁)。このインドネシア語版により、それまで多くの人にとって未知の存在であった「イ・ラガリゴ」の大要が知られるようになり、そのことが後にアメリカの前衛的演出家ロバート・ウィルソンによる「イ・ラガリゴ」の演劇化に、そしてユネスコによる「世界の記憶」認定(2011)へと繋がっていくのである。
一方、センセは戦前、オランダ植民地政府の言語行政官として「マッテス研究所」の所長を務める傍ら、文献学的諸論考を発表、さらにマッテスの業績(1885)を継承した『オランダ語-マカッサル語辞典』(Makassaars-Netherlands Woodenboek, 1979)を編纂した。
ノードュインは『18世紀のワジョ年代記―ブギスの歴史学』(Kroniek van Wadjo: Een achttiende eeuwse kroniek van Wadjo- Bugineese historiografie, 1955)を執筆出版後、聖書翻訳家を経てライデン大学でブギス語を教授した。教え子には、ブギス・ムラユ文学のトール『戦いの雄鶏-ラブアヤ王の戦勲詩』(Tol, R., Een Haan Oorlog, 1990)や、「イ・ラガリゴ」の口頭伝承としての側面を論じたコールホフ(Koolhof, S., Datuna Sawerigading: Een Scène uit de I La Galigo, 1992, unpublished)がいる。
4. インドネシアおよび英語圏におけるブギス・マカッサル文献学研究
南スラウェシでロンタラ文書を利用した研究が盛んになるのは、政治的混乱が収束に向かう1960年前後からである。マッテス研究所を継承した「南・南東スラウェシ文化協会」(YKSST)が設立され、まず『ゴワ史』(Wolhoff & Abdurrahim,Sedjarah Goa, 1959)が刊行され、さらに1967年からは同協会から歴史文化的雑誌『ビンキサン』(Bingkisan)が刊行されるようになった。また、ウジュンパンダン歴史人類学研究所からは『タロ王国史』(Abd. Rahim & Ridwan, Sejarah Kerajaan Tallo’ suatu transkripsi Lontara’, 1975)が、YKSSTからは『アマナ・ガッパの航海・取引に関する法』(O. L. Tobing, Hukum Pelayanan dan Perdagangan Amanna Gappa, 1977)などが刊行された。なお、ノードュイン(1957)によれば、アマナ・ガッパのロンタラ文書は後に、『ブギスの航海法文書』(A code of Bugis Maritime Laws)として英訳され、1832年にシンガポールで宣教師協会から出版された。17 世紀後半に編まれたブギスの航海法が19世紀にも生きていたこと示す証しになるだろう。
1970-90年代には、ロンタラ文書を扱った学位論文も現れ始め、アンディ・ザイナル・アビディン「15-16世紀のワジョ―ロンタラに基づく南スラウェシの歴史的研究」(Andi Zainal Abidin, Wajo pada abad XV-XVI suatu penggalian sejarah terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara’, 1979)、マトゥラダ「ラ・トア、古人のことば-ブギス人の政治人類学についての分析」(Mattulada, Latoa: satu lukisan analitis terhadap antropologi-politik orang Bugis, 1985)などがある。また「イ・ラガリゴ」に関しては、アンボ・エンレ「ウェレレンゲ樹を切り倒す―ブギス古典文学ラガリゴよりひとつのエピソード」(Fachruddin Ambo Enre, Ritumpanna Welenrennge: sebuah episoda sastara Bugis klasik Galigo, 1983)、ヌルハヤティ「サウェリガディンのチナ国への航海」(Nurhayatih Rachman, Episode pelayaran Sawerigading ke tanah Cina, 1999)がある。これらの学位論文はいずれもインドネシア大学に提出され、後に出版されている。
さらにこの時期に特筆すべきふたつのプロジェクトがある。ひとつはKITLVの「イ・ラガリゴ・プロジェクト」で、それに参加したM.サリムは、NBG188版全12巻をインドネシア語に初訳した。この訳業は刊行には至らなかったが、後の翻訳事業に引き継がれ、1995年には『イ・ラガリゴ』第1巻が刊行された。もうひとつは1992年から始まったハサヌディン大学のムフリス・パエニをリーダーとする「ロンタラ・プロジェクト」であり、5年をかけて総計4049点の文書が収集、マイクロフイルム化された。写本はI. 宗教関連(主に祈祷詞)、Ⅱ. ロンタラ文書(主に暦、言い伝え)、Ⅲ. 文学(主にガリゴ)の3部門に大別され、ガリゴ関連文書だけで300点近くになった。ただし、ここで言われる「ガリゴ」とは「イ・ラガリゴ」叙事詩ではなく、古い文学のジャンルを指す用語として使われている。「ガリゴ」に分類される写本の多くは、「三毛猫(の物語)」(Meongpalo karelae)と呼ばれる、村々を転々とする稲の女神サンヤン・スリとその従者である三毛猫の道中譚であり、「イ・ラガリゴ」叙事詩に直接関わるものではない。なお、これらマイクロフイルム資料は、南スラウェシ州文書館(旧国立文書館マカッサル分館)で閲覧可能である。
最後に、オランダ以外の欧米言語圏からの文献学的研究に注目すると、L.アンダヤ『アルン・パラッカの遺産』(L. Andaya, The heritage of Arung Palakka, 1981)が、オランダ語資料、ロンタラ文書を駆使してマカッサル戦争とボネ王国の隆盛を描き出した。マックナイトのもとで学んだコードウェルは、前掲の学位論文(1988)において、比較的短いロンタラ文書に文献学的考察を加え、それらの英訳を試みた。その後、ドゥルース『湖水の西側の土地』(Stephen Druce, The lands west of the lakes, 2009 )がアジャタッパレン(現在のシドラップ県)の王国史を地方伝承とロンタラ文書を活用して描き出した。一方、マカッサルのロンタラ文書研究としては、カミングスが『王たちのつながり―マカッサルのゴワ・タロ年代記』(W. Cummings, A chain of kings: The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq, 2007)、 『マカッサル年代記』(The Makassar annals, 2013)を発表しており、本格的な年代記研究の先駆けとなっている。そしてもっとも近年の研究に位置するのが、冒頭でも言及したマックナイトらによる共編訳『ブギス・ボネ年代記』(2020)である。
(後編へつづく)
