インドネシア東部、海上生活を営むサマ人らの移動に密着。漁場の名、岩の名、岬の名……それらの言葉をひとつひとつ収集し、ナヴィゲーションに関わる言葉の体系を編み上げた。「漂海民」の環境認識に言葉から迫る画期的な試み。彼らが視ている風景とは?
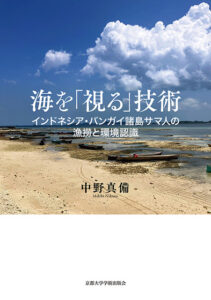
中野真備(甲南女子大学)
本書は2017年から断続的におこなった現地調査に基づくものです。現地調査では中スラウェシ州のあるサマ集落に滞在し、サマ語とインドネシア語を併用しながら、漁撈への参与観察や、漁師らに対する聞き取り調査などをおこないました。
以下、順を追って各章の内容を紹介します。
海を生きる人びとの世界(序章)
海を生きる人びとの漁撈文化には、漁撈の技術や活動だけでなく、知識や自然観、さらにそうした知識を具体的な漁撈活動で発揮する戦略や活動の仕方までもが含まれます。人間は、自身をとりまく環境を認知し、個体の活動を条件づけてきました。このような主体的環境に対して、生態人類学は実践や行為などの活動面から、認識人類学は精神面から迫ろうとしてきました。認識人類学の根源的な問いは「ある土地に生きる人びとが、その自然環境をどのように認識しているか」ということにあります。そのために土地の人びとによって用いられる概念と名称(方名)を採集し、これらを手がかりとして知識の体系(=文化)を明らかにしようとする、民俗分類学的手法が採られてきました。
ところが実際の生業活動では、当然ながらひとつの行為のなかで複数の知識の体系が用いられます。しかし、複数の分類体系を包括して捉えるような試みは多くありませんでした。植物や貝類のようにそのものを対象者に見せて方名を聞きとることができた分類体系に対して、海底の視えない空間などは手法の対象として扱いにくいものでした。また、サマ研究においても、漁撈、特にサンゴ礁以外の海域における活動を対象としたものは実は限定的でした。
そこで本書は、不可視性を備えたバンガイ諸島の海を生きるサマ人の漁撈を対象として、海上移動をめぐる生物・自然物・空間の名称や分類の包括的な分析を通して、かれらの環境認識を明らかにしようとしました。これは、サマ人漁師たちが、海に対する恣意的な意味づけを通していかに自然との関係を構築してきたか、という問いに迫るものです。
多島海を生きるサマ人の生活世界(第1章)
東南アジア島嶼部の海域世界には、かつて移動性の高い船上生活を営んでいた海民集団がいます。そのひとつがサマ人、あるいはバジョ、バジャウとよばれる人びと(以下、サマ人)です。現在では定住化を経てフィリピン南部、マレーシア・サバ州、インドネシア東部に拡散居住しています。サマ人は海ときわめて密接な暮らしを営み、独自の海民文化を築いてきました。定住化を経た現在も、かれらの主な生業は漁撈であり続けています。
本書の舞台であるタミレ村(仮名)は、中スラウェシ州の東部に位置するバンガイ諸島のなかで最大規模のサマ人集落です。バンガイ諸島は、西にマカッサル、東にテルナテと強大な政治的中心地に挟まれた海域に位置します。バンガイ諸島は海上交通の中継地としてバンガイ王国の支配を受け、同王国はさらにテルナテ王国の支配下にありました。タミレ村は、スラウェシ島東部における周期的・季節的なナマコ交易の中継地として栄えたと考えられます。現在のタミレ村は人口約4000人で、その大部分がサマ人です。ただし、ここには華人やブギス人など多様な出自をもつ「サマ人」も含まれます。
大小の岩や島、海底の視えない外海が織りなすバンガイ諸島の海は、従来のサマ研究が当然視してきたサマ人の生活世界とはまったく異なる、いわば「不可視の海」なのです。タミレ村の漁師たちは、広義の多島海ともいうべき海で、どのように漁撈を実践してきたのでしょうか。
バンガイ諸島サマ人の漁撈活動(第2章)
サマ人の漁撈活動や環境認識に関する実証的研究はサンゴ礁や汀線帯(潮の満ち引きで陸地が露出したり水没したりする潮間帯)で漁撈をおこなう地域に限られてきたため、こうした地域における漁法や知識、認識がかれらの典型例のように捉えられてきました。これに対してバンガイ諸島の海は、サマ人集落の生態環境条件としてはサンゴ礁が小規模であり、また海底が視認できない程度の浅海から外海でも漁をおこなうという特徴があります。
タミレ村の主な漁法には、網漁、手釣り漁、延縄漁、素潜り漁、ダイナマイト漁があります。このうち、浅海から外海にかけての沿岸域における手釣り漁は特に頻繁におこなわれています。サンゴ礁の海では集団的な網漁などが多くみられますが、それと比べるとタミレ村の漁撈は個人の技能に左右されやすいものです。言い換えれば、より個人の技能を発揮する余地があると考えられます。
サマ人漁師らの利用することのある漁場は少なくとも29 カ所があり、これらは海底微地形に基づいて、ラナ型、パンギリ型、ティンプス型、パマンガン型の4つにほぼ類型化されていました。漁場へ向かう漁師の視点による海上景観は、外洋にありながら複数の目標物に囲まれているという半閉鎖性外洋系海域の特徴があります。このような海では、漁師たちは岩や山、岬、湾などを注意深く観察して、舵をとり、海を進みます。そこで重要となるのが、日本ではヤマアテ/ヤマタテと呼ばれるような位置特定技術です。これは、山や岬を目印として自船の位置を特定する方法で、大きく分けると、一直線法、二直線法、連続法、そして単に一帯の景観を視るという方法があります。他にも星や鳥、海底の岩や海藻の配置を視たり、釣り糸を垂らして不可視の海底の感触を確かめたりするなど、ナチュラル・ナヴィゲーションに類する方法が利用されます。
しかし海上では、漁場そのものも進むべき道も、直接視認することができません。それでは漁師たちはどのように海洋空間を見分け、目標物を利用したナヴィゲーションをおこなうのでしょうか。
海の民俗分類と空間的配置(第3章)
まず海の空間認識の言語的側面を捉えるために、空間分類の語彙にかんする聞き取り調査の結果をもとに3つの海域を設定し、擬似的なライントランセクト法を用いて概略的立体図を作成しました。その結果、サマ人漁師たちによる海の空間分類は、海底微地形の細かな特徴には関心が払われずに形成された大分類が多いことや、大分類の中でスポット的・断続的に認識の密度が濃くなる地点が漁場であり、その密度は漁場を中心として三次元的に波紋のように広がることなどの特徴がみられました。これはサンゴ礁を利用する漁師が「面的」に全体を微細に記憶する空間認識とは異なるもので、海底の視えない海により適した「スポット的」認識といえます。
つづいて海の空間認識における空間的配置の構造を捉えるために、漁師らに漁場の地図を描画してもらいました。そこで描き出された3つのスケッチをもとに、漁師らの認知地図の特徴を分析しました。漁師らは離れ岩(トゥコー)、岬(トロー)、村や島などの目標物の位置関係に注意を払って描き示しました。一方で、船上の漁師からは視認できないはずの要素、たとえば島棚(タナー)の外縁や漁場の位置も描き込まれていたのです。また、航行するルートそのものは描かれなかったものの、GPSを用いて出漁ルートを追跡すると実際にはほぼ同じ位置を通過していました。これらのことから、漁師らは目標物それぞれの「ある地点からは視認できる」という局所性を利用してナヴィゲーションを実践し「適切な」位置に移動することで、結果的に同じような経路の航行を可能にしていると考えられます。言いかえれば、彼らの航路は目標物の視認によって初めて見出される海の「道」として特徴づけられるものでした。
それでは漁撈や海上ナヴィゲーションにおいて利用される環境の事物は、いかに見分けられ、体系づけられるのでしょうか。
魚類・漁場・目標物の民俗分類(第4章)
第4章では、漁撈で利用される魚類・漁場・目標物に対する命名方法と民俗分類の個別分析・考察をおこないました。つづいてこれらの相互関係性と海上景観との関連から、漁師の海上における視点がどのように環境認識に作用するのかを論じました。
魚類について、エイやサメを含め 330の方名を採集したところ、その表現語彙素には外洋(シッラー)や海底堤(ラナ)などかれら独自の空間分類の語彙がみられました。つづいて 29ヶ所の漁場の方名をみると、半数近くが地形・場所、つづいて生態、発見者、故事によって分類され、由来不明なものも一部含まれていました。興味深いことに、地形・場所を基準とする際、実際の漁場は遠い沖合に位置するにもかかわらず、陸や沿岸の延長線上として命名されるという特徴がみられました。目標物について、離れ岩(トゥコー)のように比較的近距離で視認されるものは、それぞれの地形や場所に微細な特徴を注意深く観察した方名が多数を占めていました。一方、遠方から視認する岬(トロー)や湾はその位置関係が詳細に把握されているにもかかわらず、由来不明あるいは曖昧な方名か、地理的範囲の大きい地形や場所に由来するものが多くみられました。天体(ママウ)はほぼ全てがサマ語の語彙によるもので、これはママウがサマ人漁師らを中心に利用されるため、特にかれら独自の天文観や時間感覚を反映していると考えられました。
以上の事例からは、半閉鎖性外洋系海域における景観の見えかたや海上ナヴィゲーションの特徴が魚類・漁場・目標物それぞれの命名に作用していること、またこれらの絡み合いのなかで方名が共有される(あるいはしない)状況の認知要因がうかがえました。
このように海に対して驚くほど豊かな知識をもつサマ人漁師たちは、いかに自然環境と関係を構築してきたのでしょうか。最終章では海上ナヴィゲーションの技法を通して、海における人間—環境関係を論じました。
海を「視る」技術(第6章)
漁撈は、他の狩猟活動とは異なり、獲物や目的地が「視えない」、かつ流動的で不安定な海を相手におこなわれるものです。漁師たちは、島や岩といった自然物に命名し、特定の「視えかた」になるように身を置くことで海上に「道」を見出すという独自のナヴィゲーション技術を培ってきました。かれらは視覚だけでなく、櫂を用いて海の音を聴き分け、釣り糸を用いて海底の「手触り」を探るなど、身体感覚を総動員して「不可視の海」を探ります。道具や自然知と結びついたこれらの身体知は、エンジンの導入などの近代的技術と擦り合わせながら継続的に実践されています。
サマ人の海上ナヴィゲーションには、継承すべき、正統な技法はありません。かれらは無数の自然物の関係性のなかに自己を定位する「視えかた」を覚え、環境の変化や個人の経験をもとに修正を重ねて、身体化していきます。
「漂海民」ともよばれたサマ人たちの移動性の高さは、政治的・社会的背景やネットワーク性、クレオール性などの観点から論じられてきました。しかし、そんなサマ人たちが移住後の環境にも容易に適応していけることのもうひとつの背景には、このように常に編み直されうる、海との関係の結びかたがあるのではないでしょうか。
カパルのみなさんへ
「海洋国家構想」を掲げるインドネシア政府の急進的な政策は、小規模漁業民との間に分断を生じさせ、海と共に生きてきた人びとの文化的背景に対する理解不足が指摘されてきました。世界最大の島嶼国であるインドネシアにおいて、「海と共に生きる」とはどういうことか、現場から捉えていくことが重要だと感じています。
本書をきっかけとして、私たちが環境とどのように結びつきながら生きているのか思いを馳せていただければ嬉しいです。カパル研究大会でお会いすることがあれば、ぜひお気軽にご意見・ご感想をお聞かせください。
