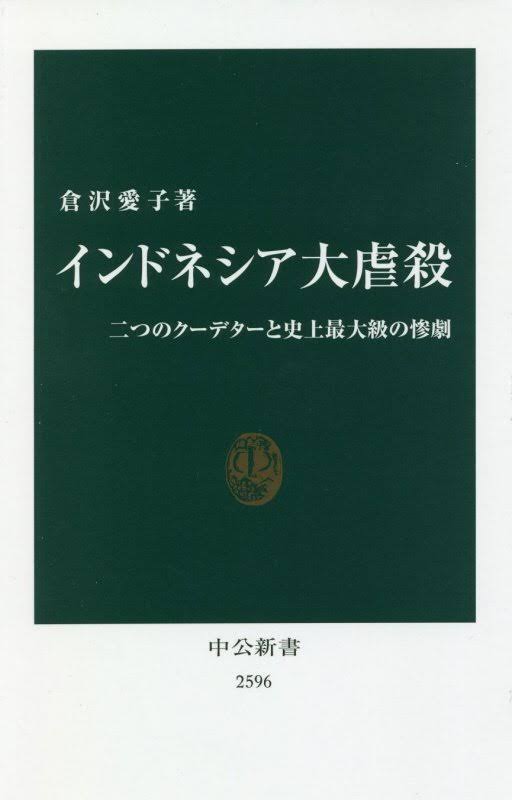聞き手: 二重作和代(京都大学大学院・院生)、野中葉(慶應義塾大学)、島上宗子(愛媛大学)
9・30事件から55年たった2020年、倉沢愛子さんが事件に関する二つの著作を出版されました[1] … Continue reading。『楽園の島と忘れられたジェノサイド:バリに眠る狂気の記憶をめぐって』(千倉書房)と『インドネシア大虐殺:二つのクーデターと史上最大級の惨劇』(中公新書)です。2014年出版の『9・30 世界を震撼させた日:インドネシア政変の真相と波紋』(岩波書店)を含めると、9・30事件をめぐる3部作といえます。
3部作の出版を糸口として、世代の異なる3人が聞き手となり、著者・倉沢さんに作品に込めた思いやインドネシア研究の後進たちへのメッセージなどを伺いました。以下では、約2時間にわたったオンライン・インタビューから、そのエッセンスを二回に分けてお届けします(以下、聞き手の言葉は太字で表記)
倉沢先生と3人それぞれとの出会い
――三人:今日はお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。
皆さんと初めて会った時のことをいろいろ考えながら、今日お会いできるのを楽しみにしていました。二重作さん、今は京都にいらっしゃるのね。以前、ジャカルタで会ったのが最後よね。
――二重作:慶應を卒業して、すぐ京大に来たので、今4年目です。学部時代、留学していた2015年にジャカルタのご自宅に行かせていただきました。それと「ルック・オブ・サイレンス」(9・30事件の虐殺を描いた映画「アクト・オブ・キリング」の続編)の上映シンポジウムが開催された時にも学生として登壇させていただきました。
2015年に早稲田でやったシンポジウムですね。野中さんに紹介していただいたのよね。島上さんとは、いつが最初かしら。
――島上:1998年頃、京大の東南アジア学フォーラムで、私、ジャワの小規模金融について発表したんです。発表を聞いた倉沢先生が東南アジア史学会で報告するよう声をかけてくださって。それが学会デビューになりました。
あなたのことはガジャマダ大学の知り合いから聞いていたし、ちょうどジャワで「開発」について調べていた頃だったから、発表、一生懸命聞きましたよ。野中さんとは、何年なるんだろうな。まだ、修士の時よね?
――野中:私が修士の調査をしていた2004年、「倉沢先生がジャカルタにいるから、会った方がいい」って知人にいわれて、勇気を振り絞って先生のお宅にお邪魔させていただいたのが最初です。その時、「野中さん、やるなら自分のテーマで世界一の研究者になると思ってやりなさい」って言われたのを良く覚えています。
そうだったかしら。でも本当に、今でもそう思ってる。そのテーマに関しては、「絶対負けない、世界一だ」ってならなきゃダメね。みんなそう言うと、笑うんだけどね。
学園闘争、最初の留学と9・30
――二重作:9・30に関心を持たれたのは、先生の学生時代の経験も大きいのだと『インドネシア大虐殺』(以下『大虐殺』)のあとがきで知りました。
ちょうど1960年代の終わり頃、学園闘争がすごかったでしょ。東大で闘争が一番激しかったのは1969年、私は大学4年生でした。いわゆる全共闘系と民青系に分かれてね、学内でものすごく対立していたの[2] … Continue reading。結局、全共闘が負けてね。その闘争は古い体質を持ったままの大学解体などを叫んで指導教授と対立していたから、全共闘系の院生は、博士課程にあがれない、就職がない、という形で追い出されて、優秀な人が研究者の道を絶たれたんですよ。そういう時代だったんですね。
その後、さらにいろんなセクトに分裂して一部が過激化して、連合赤軍のあさま山荘の事件が起こったり[3] … Continue reading。私が最初のインドネシア留学に出発したのは、1972年、その事件の2か月後ですよ。ちょうどその頃、海外に出ていった日本赤軍のメンバーは、9・30事件以降帰国できなくなったインドネシア共産党系の学生たちと、ヨーロッパやパレスチナで接点があったようです。これを後から知った時には、あの事件は決して日本人と無関係ではない、特に私世代の日本人とは接点があると感じて、身が引き締まる思いをしましたね。いろんな意味で無関係ではない、という気持ち。インドネシアの研究者を含めて、いろんなところで身近な人が関わっていたのが後でわかってきたのでね。
――野中:1970年代初頭のインドネシアでは、9・30はまだ生々しかったのでは・・・。
最初の留学の時(1972年~73年)から、9・30を意識することはありましたよ。実は留学前の1968年に学生団体にくっついて中国に行ったことがあったんですね。それが留学中に問題になったの。滞在許可を取る時に、今まで訪問した国を全部書き出せっていう欄があって、それに「Tidak ada(ありません)」と書いてしまい、それが後から嘘だとバレて、「なんで中国に行ってたことを隠してたんだ」と言われて・・。とにかく、今では考えられないほど厳しく見張られていたんです。そんなことから、とてつもない恐怖というのを最初から感じていました。これが、9・30に繋がっているということくらいは何となく分かっていて、この問題をいつかなんとかしなくちゃいけない、と思っていました。研究するまでとは思ってなかったけど、単純に知りたい、とずっと思っていました。だから続いているんでしょうね。最終的にこんなにのめり込んでやるとは思わなかったですけど。
私の最初の留学の調査許可のスポンサーはヌグロホ・ノトスサントさんだったんですよ[4]Nugroho … Continue reading。つまり、ヌグロホさんみたいな人がスポンサーについてくれないと、あの当時許可が取れなかったわけ。許可が出るまでに、二年くらいかかりましたよ。
そんな関係だったので、レバランの時にご挨拶に行ったんです。そしたらそこにオン・ホック・ハムさんが来て、床にこう(平伏)して挨拶していて、「ヌグロホさんはそんなに年上の先輩でもないのに、どうして?」と異様な感じがしたの[5]Ong Hok Ham … Continue reading。後になって、9・30事件当時ある歴史学科学生の追悼の席で不穏な発言をしたため当局に逮捕されていたオン・ホック・ハムさんを救ったのはヌグロホさんだったと知りました。ヌグロホさんは、9・30に関して現在のインドネシア政府の見解をつくった人物でしょ。スハルト新体制発足にあたって、イデオロギー的にすごく貢献した人なのよね。その人が実はオン・ホック・ハムさんを救っていた、なんてことが分かって。だから、単純な対立で見るべきではないんだなって。だからもっともっと調べてみると、これからもいろんな話が出てくるんじゃないかと思います。
9・30関連の調査 ―― かなり以前からコツコツと
――二重作:9・30については、いつ頃から調査されていったのですか?
1980年代にジャワ農村で日本占領期の調査をした時から、少しずつ情報を集めてました。村にしばらく住んでいると、そこそこの学歴があって、ある程度の社会的地位を得てもよさそうなのに、そうなってない人っていうのが見えてくるんです。そういう人たちが、ほとんど、元政治犯で釈放された人たちだったんです。
政治犯の人は、村の中では皆知られているんです。だけど、もちろん誰も私には言わない。私もずばり聞けないから、日本占領期のことから話を広げていきました。そういう人たちは大概、日本占領期にも青年団とか、重要な役割を担っているので、そこから入って、ライフヒストリーを聞いていきました。例えば、話に食い違いが出てきたり、経歴が途切れたり、村にいなかった時期が分かったりすると、そこは刑務所に入ってた時期かなとか推測できる。で、今度は別の人に、こっそり聞くと、「うん、実はそうなんだよ」と言って教えてくれたり。
――島上:スハルト時代は、9・30を調べているとは言えなかったですよね。
それは無理でしたね。でも、「農村コミュニティの変容」というテーマで調査をしていたので、聞き方を工夫して、直接9・30は出さずに、スハルト政権の初期にどういう変化があったのかを聞いていったんです。我慢しながら、小出しに聞いていきましたよ。100分あったら5分くらいしか聞きません。それでも2回3回と行くと、だんだん、話が分かってくる。まぁ、粘らなきゃだめですね。だから、若い方へのメッセージとしては、粘りなさいということ。インタビューは1回じゃ絶対ダメ。何度も何度も、これぞと思う人には粘って食いついていかないと。
調査・インタビューの妙技 ―― 現場重視、mancing、粘り
バリ島南西部のジュンブラナでの初めての調査には、野中さんも一緒に、東ジャワから行きましたよね。
――野中:ジャワからフェリーに乗ってバリに渡って、ここは、デンパサールよりも、ジャワ島のジェンベルやバニュワンギに近いんだ、という感じがしました。
そういう感覚はありましたね。それって大事なことです。バリ州のジュンブラナ県というと、どうしてもデンパサールと繋がっていることを考えてしまうけれど、人びとの生活レベルでは、必ずしもそうではないところがある。特にジュンブラナ県は相対的にムスリム人口が多いんですけど、その人たちは、全然デンパサールなんか向いていない。バニュワンギや、その先にあるジェンベルを見てるわけです。だから、プサントレン(イスラーム寄宿学校)も東ジャワに行くわけ。そういうことも、野中さんと一緒に、実際に行ってみて分かった。
――島上:ヌガラ(ジュンブラナ県の県都)で大虐殺があったということは、どう知ったのですか?
それは、バリの『ジェノサイド』にも書きましたけど、ネガラから車で45分くらいのところに、毎年ゼミ生たちが研修しているプンゲラゴアン村があるんです。2005年からだからもう15年になります。そこのコテージの従業員と話していて、聞いたんです。
――二重作:従業員の方も、よく話をしてくれましたね。
やっぱり最初のころはね、「いや、ここは何にもないよ。ムスリムとの関係もすごくよかったし」というような話しか返ってこなかったんです。だけど、ある時、私が「別の村で、ものすごい虐殺の話、聞いちゃった」って、言ったことがあったんです。そしたら競争心を煽っちゃったみたいで、「え、そんなのうちの村にもあるよ」とか言って、口滑らせちゃって・・・(笑)。そこからは、彼も後には引けなくなって、どんどん教えてくれるようになったの。
――野中:先生、それって意図的に吹っ掛けてるんですか。インタビューのテクニック?
なんかひとぎき悪い~(笑)。Mancingですよ、釣ってるところは多少あると思う。だからね、インタビューってやっぱり厳しくならないとダメ。
特に、この種のトピックは短期間の調査だとやっぱりとても難しい。かなり強力な協力者を探すか、あとは長く住み着いて、人びとのふとした時の言葉尻を捕えていくか、それじゃなきゃダメね。だから言いたいのは、粘り!粘りと時間!ホントに聞きたいと思ったら、しばらくそこにいなきゃダメ。
――島上:常にアンテナ張って、引っかかりそうなことをちゃんと掴むってことですね。本気でやっていることが相手に伝わると、協力者にも出会えていくのでしょうね。
それはそうですね。この問題を調べてほしいと思っている人たちであれば、動いてくれますね。いい加減じゃなくて、本気でやるんだっていうのは示さないとダメですけどね。
脚注