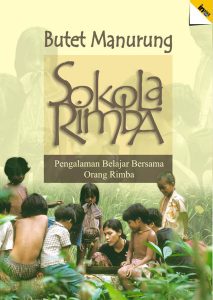森の学校―森棲みの人々の学校とは、その模索を通じて綴られた女性活動家の自伝的民族誌
Butet Manurung, Sokola Rimba (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2013), xxviii+348 pages, Rp. 79,000
評者:大澤隆将(総合地球環境学研究所 研究員)
「森の学校」をめぐる自叙伝
“Aku merasa berkewajiban untuk menjelaskan setiap pilihan yang dihadapi Orang Rimba secara fair, tanpa agenda apa-apa. […] Agendanya tidak ada, selain kemandirian Orang Rimba itu sendiri dan kebahagiaan versi mereka.” (pp. 234-235)
私は、オラン・リンバが直面するひとつひとつの選択肢について、なんらのアジェンダも持たず中立な立場から説明する責任があると感じている。(中略)アジェンダなどない。あるのは、オラン・リンバの自立と彼らが望む形の幸せだけだ。
本書は、著者ブテット・マヌルンがジャンビ州のブキット・ドゥアブラスの森林に暮らすオラン・リンバの子どもたちに文字の読み書きのてほどきを開始し、その4年後、みずからのNGOを設立するに至る過程を自伝的に描いた一般向けの書籍である。2007年の初版から重版・改訂が繰り返され、2012年に英語版が発刊されたのち([英語版]参照)、2013年には映画化がなされた。また、2003年に彼女により設立されたNGO-Sokola Rimba、すなわち「森の学校」―は、今ではジャンビのほかパプアやハルマヘラでも教育活動を展開している。書籍、映画、そしてNGO活動のそれぞれが数多くの賞を受けており、本書はインドネシアにおいて知名度の高い作品である。
本書は二部構成をとっている。第一部では、1999年9月に環境保護団体WARSIの一員として著者がブキット・ドゥアブラスを訪れた日から始まり、約1年間にわたる森の中での出来事と活動が日記の体裁をとって記述される。森林内での生活、オラン・リンバとの交流、そして数々の困難を乗り越えながら徐々に教育の方法を確立していく過程が、著者の素直な感情や思索、時にはユーモアを交えながら軽妙に語られる。
第二部では一転して、同地における計4年間の教育を継続・成功させた視点から、随筆的な体裁で自身の活動の意義について内省するとともに、その後のNGOの活動展開を記述している。その中で、WARSIとの決別、ブキット・ドゥアブラスからの離脱、自ら主宰するNGOの設立と他の地域への展開、そして数年後に再訪したブキット・ドゥアブラスで目のあたりにしたオラン・リンバの社会の変化が描写されている。2013年改訂版には、エピローグが追加されており、2012年の視点から、更なるオラン・リンバの社会の変化と、自身が主催するNGOの活動が描写される。
本書に通底するのは、著者によるオラン・リンバの文化社会を真摯に受け入れようとする姿勢と、オラン・リンバと彼らが暮らす森林環境に対する深い愛情である。しかしながら、本書の価値は単なる追想にとどまらない。著者ブテット・マヌルンは、ブキット・ドゥアブラスでの活動を始める以前にパジャジャラン大学で人類学を専攻していた。また本書で描かれた経験ののち、オーストラリア国立大学で応用人類学の修士号を取得している。本文の中でもしばしば「人類学」に言及がなされ、少なからず人類学的民族誌を意識しながら書かれている。このような意味で、本書は日記的な自叙伝であり、教育の実践書であると同時に、民族誌としての側面を持つ。以下に、人類学者としての視点からオラン・リンバについて解説をおこない、本書に対する関連する考察を行ったのち、最後に民族誌的な価値について論評を行う。
「部族」としてのオラン・リンバ
オラン・リンバ(Orang Rimba)は、ジャンビ州のブキット・ドゥアブラスをはじめとするスマトラ島南部の森林地域に暮らす人々で、インドネシア一般には他称の「クブ」(Kubu)の名で知られる。バンド単位で森林内の移動を繰り返す彼らの狩猟採集民としての生活様式は、周囲に暮らすマレー人とは異なる「未開」な部族として、オランダ植民地時代から調査・研究の対象となってきた(Persoon1998: 509-510)。
インドネシア共和国の独立から間もない時期に、当初少数の集団が指定された「孤立民族」(suku terasing)に関する政策指針の中で、「クブ」は「極端な貧困状態にある人々」としてすでに指定・言及されている(Persoon 1998: 287)。これに続くインドネシアの国民国家形成過程の中で、オラン・リンバに対して同化政策が取られた。この同化政策においては、物資の提供、農業技術の導入、(場所によっては強制移住を含む)定住集落の建設と医療サービスの提供が行われたが、効果は限定的であった(Duncan 2004; Persoon 1998: 287)。
1990年代に入ると、大規模産業や農地拡大の森林侵食に対抗した環境保護運動が高まりを見せる。ジャンビ州ではWARSIをはじめとする環境系NGOが森林保護を目的とした活動を開始するのと並行して、その森林で暮らしてきたオラン・リンバの人々への援助を開始する。彼らの森の中での生活はNGOの広報活動やメディアを通して、一般の人々にも広く知れ渡ることとなる。結果として、オラン・リンバはインドネシアにおいて、ある種の差別感覚を含んだ「未開の部族」としての象徴的な立場にあると同時に、近年では「森林と共生する人々」として環境保護運動(および先住民権保護運動)の象徴的な立場として語られる存在となっている(Li 2000)。
このように、オラン・リンバは森林に暮らす「未開の部族」とみなされてきた歴史を持つが、彼らは決して文明や国家から隔絶し、孤立してきたわけではない。オラン・リンバはジャンビ州や南スマトラ州にかつて栄えたマレー国家の上流―下流交易において、上流部における森林産物の採集・供給者の役割を果たしてきた歴史を持つ。オランダ植民地時代の記録には、彼らは周囲のマレー人と、籐、樹脂、自生のゴム(jertung)といった森林産物の交易を行ってきたことが記されている (Andaya 2008: 204-208; Persoon 1989: 510-512)。また、歴史上、少なくない数の集団がマレー国家に従属し、マレー人と同化されて来たことが記されている(Andaya 2008: 207-209)。
現在においても、ブキット・ドゥアブラスで暮らすオラン・リンバの人々は森林の境界域に暮らすマレー人との間で交易をおこなっており、蜂蜜、籐、樹脂、染色用の木の実(jernang)などを売却することで、服、食料、塩、バイクなどを購入している。森林の周縁部にコンクリートの住居を建て、定住を選択している人もいる。
すなわち、オラン・リンバの「部族」としての立場は、歴史的な個々人の「選択」に大きく依っている(cf. Benjamin 2002)。もちろん、この選択は個々人の意思によって随時自由に決められる性質のものではなく、国家あるいはマレー人との関係性や彼ら自身が持つ文化的なロジック(cf. Sandbukt 1984)によって制約されたものである。しかしながら、これらの制約の中での限られた選択肢から、森林の中で暮らすことを選択した人々がオラン・リンバとしての生活を送っているとみなすことが出来る。
彼らの選択に寄り添うということ
このような「選択」を軸に置きながら本書を読むと、非常に興味深い。本書の中で、教育活動を進めるにあたり数々の困難に著者は直面するが、その大きなものはオラン・リンバからの著者に対する拒絶である。この拒絶という選択の背後にあるのは、オラン・リンバの持つさまざまな文化的なロジックである。すなわち、外部の人間を「明るい人」(orang terang:森の中で暮らすオラン・リンバと対置される)として区別する姿勢、外部の者の干渉が精霊の怒りをもたらすとする信仰、死者が出た際の宿営地の移動、上の世代に見られる文字への無関心、さらにはオラン・リンバが免疫を持たない伝染病を森の中に持ち込まれる恐怖、などなどを理由として、著者はしばしばオラン・リンバの人々から拒絶される。経験をもって共有される、単一ではない多様な文化的ロジックに基づきながら、オラン・リンバが外の世界との交流を拒絶する選択をしてきたことが読み取れる。
このような拒絶を受けながらも教育活動を続けることに関し、著者は第一部の日記描写のなかで、教育がオラン・リンバにとって具体的に利益のあることであることを主張し、自らの活動を正当化する。すなわち、読み書きを習得することで、マレー人との商取引において取引量を胡麻化されることを防げる、また、外部者に侵食されつつある森林の土地契約をおこなう際に契約書を確認できる。結果として、オラン・リンバは自らの生活様式と森林環境を保護していけるという彼らにとっての利益である。ここでは、著者の見解はあまりに楽観的に感じられる。著者による基礎的な数字とアルファベットの読み書きのてほどきを通して、商売や土地契約書の内容を精査し、外部の人間との権力・知識の差を覆すことは現実的には不可能と思われるからである。
しかしながら、第二部において著者とWARSIとの活動方針の相違に苦悩する中で、このような姿勢はより抽象的で読者に納得のいく形に昇華される。著者が一つの結論として記すのが、本書評の冒頭に引用された言葉である。ここでは、読み書きの教育を続けていくことを通して、彼らの選択肢を広げようとする決意表明が示されている。そしてこの姿勢は、WARSIの活動に見られる、一定期間内に獲得した生徒の数で教育活動の成果を評価しようとする姿勢、また森林居住者の文化保護的な立場からオラン・リンバが外の世界の物品・技術を導入することに難色を示す姿勢―すなわち官僚的な活動方針あるいは「アジェンダ」に基づいた活動をおこなおうとする姿勢―とは相いれないものである。著者自身(と、この活動の協力者)が、文字通りライフワークとして、オラン・リンバの読み書きの教育に携わっていくという、決意表明である。
さらに著者は、基礎的な読み書きをほどこした上でのさまざまな選択決定は、オラン・リンバ自身の価値観に基づいて行われるべきものであると考えている。事実、著者は読み書きと医療に関すること以外、オラン・リンバの社会に干渉をしようとはしない。本書の終盤で描かれるオラン・リンバの社会的な変化も、ありのままに受け入れようとしている。
著者が目指すのは、家父長的な保護・干渉の姿勢に基づきながら、オラン・リンバを啓蒙し改宗させることでも、定住させて「田舎の普通のインドネシア人」にすることでも、森林環境や彼らの伝統的な生活様式を保全していくことでもない。ただ、彼らに寄り添い、彼ら自身がとることが出来る選択肢の可能性を広げることだけを目指している。
現代的な開発・援助計画(あるいは研究プロジェクト)は、官僚機構的なアジェンダ、スケジュール、数値目標、そして資金管理の中で進行し、時にこれらが制約となり本質的な目的を見失う場合が往々にしてある。しかし、人々にライフワークとして寄り添おうとするこの決意表明は、それらに対する強烈なアンチテーゼと感じられる。私自身、有期の研究プロジェクトに関わる人間として、先住民を対象とする人類学者として、さらに敷衍して人間を相手に研究を行うフィールド研究者として、自らを省みる示唆を与えてくれる。
一人称語りの民族誌として
アカデミックな視点から本書を批評するならば、指摘されるべき点は多い。たとえば、民族誌的描写の中で沸き起こる驚きや疑問が掘り下げられていない点、オラン・リンバのものの見方そのものを洞察しようとはしていない点、オラン・リンバの個人・集団の志向の多様性が十分に検討・反映されていない点、などを挙げることができるだろう。
しかしながら、一人称語りを基礎とした文章には、彼女自身が見た世界そのものとしてのリアリティと力強さがある。そして、一つのトピックに固執せず、自分の目で直接見た出来事、自分の感情や思索、そしてそれに対する自分の行動を、軽やかに、時には率直すぎる筆で描く姿勢は、エキゾチズムの過強調や「善き野蛮人」(bon sauvage)像の再生産といった、ポスト・モダン的批評を寄せ付けない。
このような描写は、彼女の素直な感受性、ユーモアを含む感情表現、鋭い観察眼、そして繰り返しになるが、オラン・リンバの文化・社会に対する真摯な態度と、オラン・リンバと彼らが暮らす環境に対する深い愛情に裏打ちされている。
本書は、専門書としての民族誌がどこかの時点で失ってしまった、自分を中心としたものの見方と感情の大切さを読者に再認識させてくれる。そして、一般書としての民族誌の可能性を切り開いているという意味で、優れた作品である。このような意味で、専門外の人はもとより、NGO関係者そして専門の社会学者・人類学者にお勧めしたい内容である。
kapal運営委員会情報担当より
今回、「先住民」をキーワードとして、「カパルの本棚」と「カバル・アンギン」の連動企画による2本の投稿を掲載いたしました。
「カパルの本棚」では、ジャンビ州のオラン・リンバ(森の人)に対する教育活動を主題とする『Sokola Rimba』の書評を、リアウ州の先住民研究を専門とされている大澤隆将さんにお書きいただきました。
また、「カバル・アンギン」では、国立民族学博物館の特別展「先住民の宝」の実行委員長である信田敏宏さんに、同展の紹介とともに、信田さんが専門とされているマレーシアの先住民とインドネシアの先住民の問題を対照していただきました。
お二人は文化人類学者ですが、内容は文化人類学に限るものではなく、さらなるインドネシア理解・東南アジア理解につながる興味深い内容です。双方を合わせてお読みいただければ幸いです。
[英語版]
Butet Manurung (2012) The Jungle School. (trans.) A. Robertson & T. A. Daenuwy. Xlibris Co.: Jakarta.
[参照文献]
Andaya, L. Y. (2008) Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Strait of Melaka. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Benjamin, G. (2002) ‘On being tribal in the Malay World’, in Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives. (eds) G. Benjamin & C. Chou. Singapore: International Institute of Asian Studies.
Duncan, C. (2004) ‘Legislating modernity among marginalized’, in Civilizing the Margins: Southeast Asian Government policies for the Development of Minorities. (ed.) C. R. Duncan. Ithaca: Cornell University Press.
Li, T. M. (2000) ‘Articulating indigenous identity in Indonesia: Resource politics and the Tribal Slot’. Comparative Studies in Society and History 42(17): 149-179
Persoon, G. (1989) ‘The Kubu and the outside World (South Sumatra, Indonesia): The Modification of Hunting and Gathering.’ Anthropos 84(4/6): 507-519.
Persoon, G. (1998) ‘Isolated groups or indigenous peoples Indonesia and international discourse.’ Bijdragen tot de Taal-. Land- en Volkenkunde 154 (2): 281-304.
Sandbukt, Ö. (1984) ‘Kubu conception of reality.’ Asian Folklore Studies 43(1): 85-98.